こんばんは
ダムに沈んだ村、の記事がとても好評です。
未だに、「ダム 沈んだ村」で検索すると下記の記事がトップに出てきます
こんな弱小ブログの記事がトップに出てくるくらい、ダム建設によって沈んだ村、にフォーカスした記事は少ないです。
ということで思いつく限り私の方で調査してまとめていきます!
まずは北海道、東北編です!
後は下記のダムの説明で出てくる言葉をいくつかまとめておきます!
・水源地域対策措置法
1974年に制定。ダム建設によって水没する地域の補償について定めた法律。
通常指定ダムと9条指定ダムというのがあり、後者はさらに多くの家屋、農地が水没するダムが対象

ダム建設の補償の基準がないことで各地で争いが起きたことから制定された法律のようです
この法律制定以前はだいぶ水没側の村に不利な条件で建設された村があるとかないとか
着工年が古い順に紹介します
【福島県】田子倉ダム
河川一等兵 – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
福島県と新潟県の県境、只見川にある田子倉ダム。周辺は日本有数の豪雪地帯として知られています。
ダムの概要
- 堤高: 145m
- 堤頂長: 462m
- 総貯水容量: 4億9400万㎥
- 利用目的: 洪水調節、発電
- 型式: 重力式コンクリート
- 事業主体: 電源開発
- 着工年/竣工年: 1953年/1960年
- 移転世帯: 110戸
- 所在地: 福島県南会津郡只見町
ダムの歴史と背景
このダムで水没した田子倉集落は、立地を見ての通り山奥だったのですが、林業で儲かっており、他の集落より生活水準が高い状態でした。
そのため、住人は反対運動を激しく繰り広げ、相場と比較して明らかに高い金額の補償金を、福島県知事経由で建設元の電源開発に要求し、早く事業を進めたい電源開発側はそれを一旦受領します。

新築の建売価格の3~7倍(現在の価値で言うと3億円くらい?)
といわれているそうです。
ただ、それにNGを出したのが、現国交省と経済産業省(発電関連なので)です。

そんな法外な値段で補償するという約束を結んではいかん!
今後の公共事業でも同じような補償を求められ、国も県も財政が苦しくなるぞ!
というのが理由です。
結果的に通常の金額の補償に落ち着きますが、他のダム建設予定地の住民が補償金のつり上げを要求するという社会問題となりました。
これを、田子倉ダム補償事件と呼ぶそうです
今まではダム建設の都度交渉していたのですが、一定の基準(法律)の上で保障されるべきだよね、という風潮が広がり、結果的にこの田子倉ダム補償問題は、様々な法律が制定されるきっかけになりました。
【福島県】奥只見ダム
パブリック・ドメイン, リンク
次はめちゃめちゃ山奥にあり、アクセスが難しいことで有名な福島県の奥只見ダムです
ダムの堤高は157mと日本第3位の高さを誇ります。
ダムの概要
- 堤高: 157m
- 堤頂長: 480m
- 総貯水容量: 6億100万㎥
- 利用目的: 発電
- 型式: 重力式コンクリート
- 事業主体: 電源開発
- 着工年/竣工年: 1953年/1960年
- 移転世帯: 38戸
- 所在地: 福島県南会津郡桧枝岐村、新潟県南魚沼市
めちゃめちゃ有名なダムですが、こちらでも補償に伴うやり取りが行われていました
地理的にも田子倉ダムと近く、同じように交渉が行われたようです
【岩手県】湯田ダム
河川一等兵 – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
次は、岩手県和賀川にある湯田ダムです。このダムは興味深いポイントがたくさんあります!
ダムの概要
- 堤高: 89.5m
- 堤頂長: 254m
- 総貯水容量: 1億1,400万㎥
- 利用目的: 洪水調節、不特定利水、発電
- 型式: 重力式アーチダム
- 事業主体: 国土交通省
- 着工年/竣工年: 1953年/1964年
- 移転世帯: 530戸(旧湯田町)
- 所在地: 岩手県和賀郡西和賀町

型式は重力式アーチで全国に12機しかありません
後は移転世帯が530ととても多い、見どころが多いダムです
ダムの歴史と背景
湯田ダムの建設により、旧湯田町の広範囲が水没し、約530戸という大規模な住民移転が発生しました。さらに、水没範囲には鉄道、鉱山、水力発電所なども含まれ、建物、土地の補償だけではなく、様々な利権が絡む非常に大変な交渉が求められました。
さらに、これと同じタイミングで上述した田子倉ダム補償事件が起き、それも補償の交渉が長引く要因となりました。
最終的には、水没基準補償と湯田ダム水没者厚生大綱というものが発表され、交渉は妥結しました。
その過程はダム建設における補償問題の困難さを象徴する出来事として、後世に語り継がれており、その後のダムの補償の基準(水源地域対策特別措置法など)の制定にも影響を与えたと言われています。
現在、湯田ダムは地域の治水・利水に重要な役割を果たしており、ダム湖畔には水没した村の歴史を伝える施設が整備されています。
【秋田県】玉川ダム

河川一等兵 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる
秋田県の田沢湖からほど近い玉川に位置する玉川ダムは、単なる治水や発電のためだけでなく、ある特殊な目的を持って建設されたダムです。
ダムの概要
- 堤高: 100.0m
- 堤頂長: 480.0m
- 総貯水容量: 2億2,500万㎥
- 利用目的: 洪水調節、不特定利水、農業用水、発電
- 型式: 重力式コンクリート
- 事業主体: 国土交通省
- 着工年/竣工年: 1973年/1990年
- 移転世帯: 約100世帯
- 所在地: 秋田県仙北市
ダムの歴史と背景
多摩川ダムが建設された玉川は、強酸性の水が流れることで知られていました。この酸性の水は、下流の田沢湖や玉川の生態系に深刻な影響を与え、特に田沢湖の固有種であるクニマスを絶滅させる原因にもなったと言われています。
ダム建設は、この酸性水を中和するという重要な役割を担っていました。ダム湖に石灰石を混ぜる中和事業行うことで、水質を改善し、下流の環境を守るというユニークな目的があったのです。
建設に伴い、旧玉川村の集落などが水没し、約100世帯が移転を余儀なくされました。日本のダム史上でも珍しい「環境改善」という目的を果たしました。

補償自体は粛々と行われたようですが、目的が面白いダムです
【山形県】寒河江ダム
河川一等兵 – 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる
山形県を流れる寒河江川に建設された寒河江ダム。そのダム湖は、月山のふもとに広がることから**「月山湖」**と名付けられました。このダムは、多くの人々の暮らしを支える一方で、故郷を水底に沈めるという歴史を刻んでいます。
ダムの概要
- 堤高: 123.5m
- 堤頂長: 440m
- 総貯水容量: 1億5,100万㎥
- 利用目的: 洪水調節、不特定利水、発電、上水道
- 型式: ロックフィルダム
- 事業主体: 国土交通省
- 着工年/竣工年: 1972年1990年
- 移転世帯: 136戸
- 所在地: 山形県西村山郡西川町
ダムの歴史と背景
寒河江ダムの建設により、旧朝日村にあった大朝日という集落が水没しました。ダムが完成するまで、この地には136戸の家がありましたが、住民はダム建設を巡る補償交渉を、行政と良好な関係のもとで進めたとされています。
移転にあたっては、住民が協力して新たな生活の場を探し、集落ごとまとまって移転する「集団移転」を望みました。その結果、コミュニティの結束を保ったまま、新たな地で生活を再建することができたのです。
このような協調的な補償交渉は、他のダム建設における厳しい対立とは一線を画しており、ダム開発史の中でも特筆すべき事例として知られています。
現在、ダムは下流域の治水・利水に重要な役割を果たしています。ダム湖畔には、水没した集落の歴史を伝える施設やモニュメントが整備されており、ダムの功罪だけでなく、人々の協力によって紡がれた歴史も感じることができます。

どのくらい行政とうまくやっていたかはわかりませんが下記のような記述が複数見受けられます
あながち嘘ではないでしょう
多くのダム建設予定地では「ダムによって栄えた村はない」として反対の姿勢を崩さなかったが、西川町に関しては「ダムが出来てつぶれる町村は、出来なくても何れつぶれる」という発想でむしろダムを起爆剤として町興しを図る政策に転じた。
wikipedia(寒河江ダム)より
それは双方が信頼関係を築いていたからであろう。この信頼関係は、次のような先例視察のことからも理解できよう。
http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/TPage.cgi?id=435#:~:text=%E5%AF%92%E6%B2%B3%E6%B1%9F%E3%83%80%E3%83%A0%E3%81%AE%E8%A3%9C%E5%84%9F,%E6%89%80%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
【青森県】津軽ダム

Qurren, CC 表示-継承 4.0, リンクによる
次も青森県。下記の諸元にある通り、2016年にできた比較的新しいダムです
青森県の白神山地のど真ん中にあります。
ダムの概要
- 堤高: 97m
- 堤頂長: 342m
- 総貯水容量: 1650万㎥
- 利用目的: F(洪水調節), N(不特定利水), A(農業), P(発電), W(上水道), I(工業用水)
- 型式: 重力式コンクリート
- 事業主体: 青森県
- 着工年/竣工年: 1988年/2016年
- 移転世帯: 177戸
- 所在地: 青森県中津軽郡西目屋村
ダムの歴史と背景
ダムの建設目的が多岐にわたるところからもわかる通り、青森の特産米とりんごの栽培などを支える、とても重要度が高いダムです。
元々、1960年竣工の目屋ダムというのがありましたが、それの60m下流に形で作られました。(目屋ダムは水没)
ダム建設の難しさは、「犠牲になるのは上流、恩恵を受けるのは下流」というところにあります。そんな中で、目屋ダム建設の際には下流の人が上流の人に米を一握り提供する、「米一握り運動」なるものが実施され、無事目屋ダムは建設されました

現在の価値換算で大体3000万くらい集まったとのこと
そんな助け合いがあるとは、いい時代だね!
しかしながら、その目屋ダムでは手狭で、津軽ダム建設の話が出ます。
もともと目屋ダムを建設で故郷を離れた人が、さらに移転を強いられることになってしまい、大きな反対運動が起こったダムとしても有名なようです

2度の移転はちょっとかわいそうかも、、、でもとても難しい問題ですね
津軽ダムのwikipediaやこちらのページも見てみてください
参考
各ダムのwikipediaのページ
まとめ
過去様々なダムが様々な経緯で建設されたという事実が分かったと思います
次は関東地方編を作成する予定です!


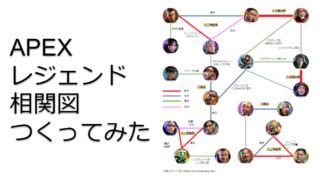





コメント